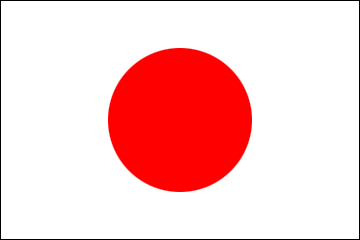【ICAOで働く日本人職員のご紹介】 宇都宮美恵 航空技術局 技術オフィサー(サーベイランス担当)
平成30年2月6日
現在ICAO事務局では9名の日本人職員が活躍しています。今回は航空技術局の技術オフィサー(サーベイランス担当)として民間航空機の安全運航に不可欠な管制システムの中でも特に重要な航空機の運航監視体制の構築,維持という重責を担う宇都宮美恵(うつのみや・みえ)さんに,お仕事の内容やICAOで働くことになったきっかけを伺いました。
宇都宮さんが所属されている航空技術局や現在のお仕事について教えて下さい。

ICAOの事務局には5つの局があり,1つが総務や人事等を取り扱い,1つが法律や渉外関連,残りの3つが航空に直接関連する部局で,私が勤務しているのは,その3つの航空関連の部局の一つである航空技術局(Air Navigation Bureau,通称ANB)です。ANBは航空機の安全運航に関する技術を持った「専門家集団」というべき組織で,航空管制官出身者や私のように航空管制技術官などエンジニア出身者が所属する空域の管理や最適化を担当するセクション,パイロット出身者の多い安全運航を担当するセクションなど,世界の民間航空の安全運航を確保するための技術面での制度やフレームワークを整備する責務を担っています。
私はその中でも特に安全な航空機運行に欠かせない航空監視システム(出発・進入機の誘導及び航空機相互間の間隔設定等の管制業務に使用される二次監視レーダやADS-B等)や衝突防止装置などの国際標準・勧告方式・運用方式の策定と,それに関わる周波数要件,監視システム一般の技術的調査や標準案作成等を担当するテクニカルオフィサーとして勤務しています。年々国際航空輸送量が急激なペースで増加し,航空交通がますます過密になる一方で,現在までの運行方式や技術を維持しつつ,より安全で効率的な技術革新をも積極的に国際標準に取り込み,航空機の安全運航を確保するための最適な環境づくりのために日夜力を注いでいます。
その中でも特にメインとなる業務が,パネルと呼ばれる世界各国や国際機関から集まったその分野の専門家による技術審議会のICAO事務局側担当として,その運営に関わることです。私の担当するパネルは監視パネルですが,ANBには様々なパネルが設置されており,各パネルの下には更に個別の案件ごとにワーキンググループが設置されています。パネルは,ある特定の国の利益のためではなく,国際的公益の観点から主にICAOの標準及び勧告方式(Standards and Recommended Practices ,通称SARPs)制定や策定,改訂の作業に携わります。例えばAnnexと呼ばれるシカゴ条約附属書を改訂する場合,まずパネルにおいて議論が行われ,様々な検証を経たあと,改訂の素案が作られます。この改訂案作成に要する期間は案件によって異なり,将来に備えた改訂であれば,検証に何年もかける場合がありますし,一方で実際の機器の不具合等から発生した緊急を要する案件であれば,すぐに素案作成に入る場合もあります。
私はその中でも特に安全な航空機運行に欠かせない航空監視システム(出発・進入機の誘導及び航空機相互間の間隔設定等の管制業務に使用される二次監視レーダやADS-B等)や衝突防止装置などの国際標準・勧告方式・運用方式の策定と,それに関わる周波数要件,監視システム一般の技術的調査や標準案作成等を担当するテクニカルオフィサーとして勤務しています。年々国際航空輸送量が急激なペースで増加し,航空交通がますます過密になる一方で,現在までの運行方式や技術を維持しつつ,より安全で効率的な技術革新をも積極的に国際標準に取り込み,航空機の安全運航を確保するための最適な環境づくりのために日夜力を注いでいます。
その中でも特にメインとなる業務が,パネルと呼ばれる世界各国や国際機関から集まったその分野の専門家による技術審議会のICAO事務局側担当として,その運営に関わることです。私の担当するパネルは監視パネルですが,ANBには様々なパネルが設置されており,各パネルの下には更に個別の案件ごとにワーキンググループが設置されています。パネルは,ある特定の国の利益のためではなく,国際的公益の観点から主にICAOの標準及び勧告方式(Standards and Recommended Practices ,通称SARPs)制定や策定,改訂の作業に携わります。例えばAnnexと呼ばれるシカゴ条約附属書を改訂する場合,まずパネルにおいて議論が行われ,様々な検証を経たあと,改訂の素案が作られます。この改訂案作成に要する期間は案件によって異なり,将来に備えた改訂であれば,検証に何年もかける場合がありますし,一方で実際の機器の不具合等から発生した緊急を要する案件であれば,すぐに素案作成に入る場合もあります。
お仕事のやりがいやご苦労,心掛けている点などについて教えて下さい。
 (監視パネルのメンバーたちと
(監視パネルのメンバーたちと <最前列中央が宇都宮さん>)
パネルに関わる作業に携わる際は特にですが,ある案件について,各専門家の意見を取り纏めて作業文書を仕上げる場合などは,常に中立性を保ち透明性を担保できるよう心掛けています。パネルでは技術的な側面から議論をするのですが,案件の中にはどうしても政治的な色を帯びたものも存在するのが現実ですから,例えばどこか一国の意見が解決策として最も優れていると内心思っても,個人的な肯定的コメントは控え,あくまでもサーベイランスに関わる専門知識を持つ一人の技術専門家として,技術的側面だけにフォーカスして,正しい評価が下せるような議論をリードし,中立の立場でパネルを最適な方向へ導くことが大切だと考えています。
また一方で,技術的にいくら優れたものであったとしても,現実的に実行可能なものであって,各ICAO加盟国が受け入れ可能な制度や提案でなくてはならないという視点を常に持つようにしています。また担当分野の専門知識という面では,自分がエキスパートであるという自負を持ちつつ,民間航空における技術的問題に常に関心を持ち,同時に日々進化する航空関連の技術をはじめ,さまざまな情報を自ら収集し,必要に応じて更新することが不可欠です。同僚に具体的な技術的分野での直接的アドバイスを仰ぐことは,担当が細分化されて専門的過ぎるためなかなか難しいのですが,論点の整理やロジックの組み立て方,パネルの意見の取り纏め手法等についてはアドバイスを仰ぐことがあります。私と比べて経験豊富な同僚ばかりなので色々な,それも適切なアドバイスをくれることが多く,ICAOで働く上でとても頼もしく思います。ちなみに数年前にANB内の組織改編を契機として,主担当のサーベイランスの分野に加え,最近では航空関連の周波数調整の分野や,遠隔操縦や無人機といった次世代の課題にも携わるマルチタスクとなり,業務量は増加しています。限られたマンパワーの中で効率的に作業をこなせるよう心掛けています。
また一方で,技術的にいくら優れたものであったとしても,現実的に実行可能なものであって,各ICAO加盟国が受け入れ可能な制度や提案でなくてはならないという視点を常に持つようにしています。また担当分野の専門知識という面では,自分がエキスパートであるという自負を持ちつつ,民間航空における技術的問題に常に関心を持ち,同時に日々進化する航空関連の技術をはじめ,さまざまな情報を自ら収集し,必要に応じて更新することが不可欠です。同僚に具体的な技術的分野での直接的アドバイスを仰ぐことは,担当が細分化されて専門的過ぎるためなかなか難しいのですが,論点の整理やロジックの組み立て方,パネルの意見の取り纏め手法等についてはアドバイスを仰ぐことがあります。私と比べて経験豊富な同僚ばかりなので色々な,それも適切なアドバイスをくれることが多く,ICAOで働く上でとても頼もしく思います。ちなみに数年前にANB内の組織改編を契機として,主担当のサーベイランスの分野に加え,最近では航空関連の周波数調整の分野や,遠隔操縦や無人機といった次世代の課題にも携わるマルチタスクとなり,業務量は増加しています。限られたマンパワーの中で効率的に作業をこなせるよう心掛けています。
本部での業務のほかに,各国への出張も頻繁にあるようですね。
各加盟国の実務担当者との調整や意見交換や,関連する国際会議に出席するなどの出張が最近増えてきています。直接担当者と顔を合わせ,また現状を自分の目で把握することはとても重要ですし,実際にその場に行って見聞きしなければわからない事や得られない情報もたくさんあります。今直近に控えているのが,新たに担当することになった通信周波数の分野に関する案件で,まもなく某先進国へ出掛けます。世界的な通信需要の爆発的な増加を受けて,特に先進国では通信周波数の全体的不足が問題となっており,「航空に割り当てられた周波数帯を国際航空の安全航行のために守る」ということがICAOの重要な任務の一つとなっています。
今回の案件は,某国において,航空管制周波数帯に航空と関連のない商業機器の運用が認められたため,当該国における電波干渉の可能性と安全運航への重大な懸念が指摘されており,周辺各国からも状況を懸念する声が出ています。本件は,利害関係官庁の国家内の力の問題もあり,また地域間の調整等もあり,なかなか複雑です。一部の影響力の強い先進国の取組が,必ずしも先進国と同じように状況を管理することができない発展途上国に無制限に広がってしまうことが危惧されており,悪しき国際標準とならないようにするためにも,とても責任の重い役目だと思います。
今回の案件は,某国において,航空管制周波数帯に航空と関連のない商業機器の運用が認められたため,当該国における電波干渉の可能性と安全運航への重大な懸念が指摘されており,周辺各国からも状況を懸念する声が出ています。本件は,利害関係官庁の国家内の力の問題もあり,また地域間の調整等もあり,なかなか複雑です。一部の影響力の強い先進国の取組が,必ずしも先進国と同じように状況を管理することができない発展途上国に無制限に広がってしまうことが危惧されており,悪しき国際標準とならないようにするためにも,とても責任の重い役目だと思います。
ICAOで働くことになったきっかけと,ICAOや国際機関で働くことを目指す人へのアドバイスをお願いします。
 (スタッフ家族向けイベントにて
(スタッフ家族向けイベントにてお子さんと)
私は航空保安大学校航空電子科を卒業し,約8年国土交通省航空局で航空管制技術官をしていました。函館空港,仙台空港での現場経験を経て,東京の本省へ異動した時に転機が訪れました。本省では日本の航空政策のコアな部分に携わっているという大きなやりがいも感じられる一方で,朝から夜遅くまで業務に追われる多忙な環境でした。そのような中,上司の付き添いとして神戸で行われたある国際会議で,海外からの参加者がみな国際的な利益という観点から議論をしているのを耳にして,これまで自分は日本の航空政策だけを考えていただけで,国際航空の利益や発展に資するための政策という観点が抜けていたことに気付かされたのが大きな転機となりました。自分もこのような場で,海外の参加者と国際航空の利益となる政策について議論をしてみたいと思い,上司に相談したところ,スピーカーとして参加するにはまだ20年近く省内でのキャリアを積まなければならないという事実を知らされたのと同時に,リスクは高いものの大学で修士号を取得した人を対象に,国際機関への登竜門として外務省主催のJPO(Junior Professional Officer)という制度があり,そこから国際機関への就職する道があることを教えてくれました。国土交通省を退職し,大学へ戻った上でJPOの試験に挑戦することは,ある意味で安定した生活を捨てることでもありますし,大きな選択を迫られましたが,以前に父が私に話してくれた「挑戦は大きければ大きいほど克服した時の感動も大きく,難しい挑戦に出会うことで困難な問題を楽しむ心のゆとりをも育成することができる。」という言葉に背中を押され,思い切ってリスクの高い道を進むことを決断しました。そして国土交通省を退職後,大学へ戻りました。大学院進学後も奨学金試験や英語の勉強,JPO試験対策で多忙を極めましたが,同じような志を持つ社会人経験のある同級生の存在も大きな刺激となり,モチベーションを保つころができました。
そして大学院卒業後に幸運なことに,年齢制限ギリギリでJPO試験に合格し,様々な国際機関の中からICAOに派遣されました。ちなみにJPOとは,様々な国から派遣される若手のエキスパートのことで,各出身国の資金で様々な国際機関に派遣される制度です。当時ICAOに派遣されていたJPOの数は,他の国際機関と比べてかなり少なかったのですが,それでも私の他にスペインやバハマから派遣されていました。各国が費用を負担してまで,JPOを国際機関に送り込む目的は,国際機関の自国出身の職員数を増やすことであり,国際社会への人的貢献のためです。地球規模的課題が山積する現代の国際社会においては,一国単位では解決できない問題が増えており,国際政治の舞台での国際機関の役割が大きくなっています。それらの国際機関に積極的に人を送り込むことで,人的資源の面からの国際貢献というこの様な取り組みが各国により行われています。日本からも毎年数名が外務省からユネスコ,国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)や国連開発計画(UNDP)などの様々な国際機関に2年の任期で派遣されています。
ところが,実はJPOとして派遣されることと,職員としてその機関から直接雇用されることには何の関係もありません。JPOの任期が切れれば,彼らの給与は途絶えてしまいます。ですので,JPOは,JPOとして国際機関で勤務しながら,経験を積み,その任期中に自分の力で正規ポストを獲得しなけなければなりません。意外とこのプレッシャーは大きく,またポストを巡って国際的な競争となる(他の国の人々と一つのポストを巡って競う等)ことも多いため,ポスト獲得への道はかなり険しく,JPO後の正規ポストでの採用率は決して高いとは言えません。(但し,正規ポストに限らず,短期ポストを含めると,JPO派遣者の約七割が国際機関において,JPO後も引き続き勤務を続けているそうです。)
私はICAOに2010年9月に派遣されたのですが,ICAOでの正規ポスト確保の為,早々に,自分に適したポストを目指して,航空技術局内でのポスト探しを開始しました。このポスト探しは,本当に大変です。まず自分に適したポストを見つけることが何よりも重要で,適したポストを見つけたら,英語での応募用紙の記入,推薦者探し等を経て,最終的に応募書類を送付となります。そして,実はここからとても長い過程が待っています。応募書類を受け取った国際機関では,まずショートリストと呼ばれる,世界各国から送られてきた応募用紙を元に,応募者をランク付けし,上位数名に絞るという作業が行われます。その後,電話でのインタビューとなります(世界各国にいる応募者に平等に接するために,例え国際機関の内部にいようとも電話でのインタビューが行われるのです)。その後,元上司の評価を提出等の様々な過程を経て,最終的に一名に絞られ,採用ということになります。この応募から採用までの期間は,ポストによっても国際機関によっても異なりますが,半年から1年かかるといわれています。応募して,面接までいったのに,いつまでたっても結果が来ず,もう諦めて忘れていた頃に合格といわれた人が何人もいるようです。自分で言うのもなんですが,強運の持ち主でJPO1年目が終わる2011年9月に,最初の応募にして,航空技術局の正規ポストでの採用が決定しました。
ICAOや国際機関で働くことを目指す方へ!
強運にもJPO1年目で正規ポストに就くことができましたが,やはり初志貫徹,精一杯努力した結果,運が付いてきたように思います。思い切って飛び込んでみるのも,もちろん大切ですが,ただのリスクテーカーにならないように,成功するための努力をすることが重要です。また,周りを見渡すと同じ志を持った人々がいますので,情報交換しながら,楽しみながら,どんどん挑戦し,物事に取り組むことが必要だと思います。
※ 宇都宮 美恵(うつのみや・みえ)
航空技術局技術オフィサー(サーベイランス担当) (Technical Office, Surveillance, Air Navigation Bureau)
宮城県仙台市出身。航空保安大学校電子科を卒業後,国土交通省航空局勤務を経て,早稲田大学で学士,米国コロンビア大学大学院で修士を取得後,
外務省のJPO派遣試験に合格し,2年間のICAO勤務を経験し,2011年にICAOに正規職員として本採用。
そして大学院卒業後に幸運なことに,年齢制限ギリギリでJPO試験に合格し,様々な国際機関の中からICAOに派遣されました。ちなみにJPOとは,様々な国から派遣される若手のエキスパートのことで,各出身国の資金で様々な国際機関に派遣される制度です。当時ICAOに派遣されていたJPOの数は,他の国際機関と比べてかなり少なかったのですが,それでも私の他にスペインやバハマから派遣されていました。各国が費用を負担してまで,JPOを国際機関に送り込む目的は,国際機関の自国出身の職員数を増やすことであり,国際社会への人的貢献のためです。地球規模的課題が山積する現代の国際社会においては,一国単位では解決できない問題が増えており,国際政治の舞台での国際機関の役割が大きくなっています。それらの国際機関に積極的に人を送り込むことで,人的資源の面からの国際貢献というこの様な取り組みが各国により行われています。日本からも毎年数名が外務省からユネスコ,国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)や国連開発計画(UNDP)などの様々な国際機関に2年の任期で派遣されています。
ところが,実はJPOとして派遣されることと,職員としてその機関から直接雇用されることには何の関係もありません。JPOの任期が切れれば,彼らの給与は途絶えてしまいます。ですので,JPOは,JPOとして国際機関で勤務しながら,経験を積み,その任期中に自分の力で正規ポストを獲得しなけなければなりません。意外とこのプレッシャーは大きく,またポストを巡って国際的な競争となる(他の国の人々と一つのポストを巡って競う等)ことも多いため,ポスト獲得への道はかなり険しく,JPO後の正規ポストでの採用率は決して高いとは言えません。(但し,正規ポストに限らず,短期ポストを含めると,JPO派遣者の約七割が国際機関において,JPO後も引き続き勤務を続けているそうです。)
私はICAOに2010年9月に派遣されたのですが,ICAOでの正規ポスト確保の為,早々に,自分に適したポストを目指して,航空技術局内でのポスト探しを開始しました。このポスト探しは,本当に大変です。まず自分に適したポストを見つけることが何よりも重要で,適したポストを見つけたら,英語での応募用紙の記入,推薦者探し等を経て,最終的に応募書類を送付となります。そして,実はここからとても長い過程が待っています。応募書類を受け取った国際機関では,まずショートリストと呼ばれる,世界各国から送られてきた応募用紙を元に,応募者をランク付けし,上位数名に絞るという作業が行われます。その後,電話でのインタビューとなります(世界各国にいる応募者に平等に接するために,例え国際機関の内部にいようとも電話でのインタビューが行われるのです)。その後,元上司の評価を提出等の様々な過程を経て,最終的に一名に絞られ,採用ということになります。この応募から採用までの期間は,ポストによっても国際機関によっても異なりますが,半年から1年かかるといわれています。応募して,面接までいったのに,いつまでたっても結果が来ず,もう諦めて忘れていた頃に合格といわれた人が何人もいるようです。自分で言うのもなんですが,強運の持ち主でJPO1年目が終わる2011年9月に,最初の応募にして,航空技術局の正規ポストでの採用が決定しました。
ICAOや国際機関で働くことを目指す方へ!
強運にもJPO1年目で正規ポストに就くことができましたが,やはり初志貫徹,精一杯努力した結果,運が付いてきたように思います。思い切って飛び込んでみるのも,もちろん大切ですが,ただのリスクテーカーにならないように,成功するための努力をすることが重要です。また,周りを見渡すと同じ志を持った人々がいますので,情報交換しながら,楽しみながら,どんどん挑戦し,物事に取り組むことが必要だと思います。
※ 宇都宮 美恵(うつのみや・みえ)
航空技術局技術オフィサー(サーベイランス担当) (Technical Office, Surveillance, Air Navigation Bureau)
宮城県仙台市出身。航空保安大学校電子科を卒業後,国土交通省航空局勤務を経て,早稲田大学で学士,米国コロンビア大学大学院で修士を取得後,
外務省のJPO派遣試験に合格し,2年間のICAO勤務を経験し,2011年にICAOに正規職員として本採用。