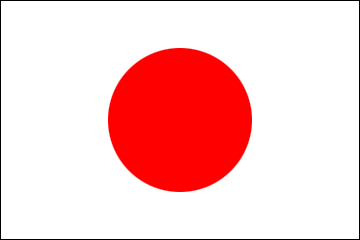代表部の活動
一つのビルの中の「地球」
私は2018年春に国土交通省からICAO日本政府代表部に出向し、ICAOの活動のうち、航空安全・航空航法分野に関する日本政府・ICAO間の調整を担当するとともに、ICAOの航空委員会の委員を務めております。着任して1年数カ月を経た経験をふまえて、活動の一部を紹介いたします。
1.ICAO航空委員会への参画

ICAO航空委員会(Air Navigation Commission)はシカゴ条約に基づき1947年に設立され、ICAO理事会に対して、シカゴ条約附属書の設定・改正を勧告するとともに、技術的な助言を行う諮問機関です。担当する分野も幅広く、19あるシカゴ条約附属書のうち航空保安及び出入国関連を除く17の附属書を担当しております。
航空委員会は、19名の委員で構成されており、3年毎に理事会が全締約国から推薦された候補者の中から選出します。世界的に調和の図られた標準を作成するため、地域バランスが考慮された構成となっており、アジア太平洋地域からは日本を含む中国、韓国、シンガポール、豪州の5か国の委員が選ばれており、日本やアジア地域の状況も考慮された標準作成がなされるよう取り組んでおります。また、標準作成において公平性を保つため、政治的な影響を受けない独立した航空専門家の立場として審議に参画することが求められております。
着任して最初の航空委員会(第208会期:2018年5月~6月)での最大の課題は,国際航空に二酸化炭素の排出権取引制度を導入するための附属書改正でした。本件は,私が国土交通省航空局に在籍していたときにも担当しており,特に2014年から2016年まで,詳細な制度設計をするためにICAOに設置された専門家グループのリーダーを務めていました。当時,自分がグループリーダーとして取りまとめた報告書が,附属書案の形に進化し,附属書として採択するための最終審議の場に航空委員として参画出来る巡り合わせに縁と喜びを感じました。そうした背景もあり,環境分野に関する知見を生かし,2019年は航空委員会内で環境等を専門的に審議するグループのリーダーを担うとともに委員会のルール・手続きを管理する作業部会の副議長を務めております。
2.とある1日


2018年10月に,2012年以来6年ぶりとなる世界航空管制会議が開催され、2週間にわたり各国航空当局幹部が議論を行いました。我が国は最近の日本での事案に鑑み,航空機からの落下物対策の重要性について国際的な取り組みを提案し,多くの国が当該会議において我が国の提案を支持したところです。この会議に先立ち,主要国への事前根回しとして,各地域の主要国への事前根回しを行いました。その最中のとある一日をご紹介します。
- 8時45分:出勤
- 9時00分:15階のフランス代表部に赴き,航空委員会で紛糾している議題(落下物とは別件)に係る打ち合わせ
をオーストラリア,フランス,カナダの航空委員と実施 - 10時30分:一度10階の執務室に戻り,資料を整理
- 11時00分:16階にあるオーストラリア代表部に赴き,オーストラリアの理事会代表(アジア太平洋諸国とりまとめ)に落下物の説明を実施
- 11時30分:14階にあるメキシコ代表部に赴き,メキシコの理事会代表(アジア太平洋諸国とりまとめ)に落下物の説明を実施
- 12時15分:アフリカ地域会合の中の一コマをもらい,3階の会議室でアフリカ各国の理事会代表に落下物の説明を実施
- 13時00分:ランチ
- 13時30分:14階にあるエジプト代表部に赴き、エジプトの理事会代表(アラブ諸国取りまとめ)に落下物の説明を実施
- 14時00分:執務室に戻り,落下物の説明に係る翌朝のUAEとのアポ入れ
このように,同じビルの中に地球が集約され、常に様々な国・地域の人たちと議論をしながら、全ての人が航空の安全・発展を考えているという環境で勤務している貴重な場所です。また、一たび業務を離れると、こうした多国籍な隣人達とテニス、サッカー、卓球、飲み会など国際交流をして親睦を深めています。
今後も、ICAO本部の恵まれた環境を生かして、航空の安全のために貢献していきたいと考えています。
代表部の「縁の下の力持ち」として

私は、ICAO日本政府代表部専門調査員として2017年4月末に着任しました。着任前のメーカー、エアラインなどでの勤務を通じて得た航空に関する知識や経験を生かして日本政府理事会代表を補佐する立場で理事会やその他の会合に出席しています。
ICAO理事会は、加盟国のうち選挙で選ばれた36カ国から構成される、常設の意思決定・執行機関です。通常、理事会は年に3回招集され、最高意思決定機関であり3年に一度開催される総会への年次活動報告や理事会議長・事務局長の任命、シカゴ条約附属書の改正審議等を行います。理事国は総会で行われる選挙で決定し、直近の第39回総会(2016年9月27日~10月6日)では、以下の36カ国が次期3カ年の理事国に選出されました。
| ●第1カテゴリー | 航空運送において最も重要な国(11カ国) |
| オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ロシア、英国、米国 | |
| ●第2カテゴリー | 国際民間航空のための施設の設置に最大の貢献をする国(12カ国) |
| アルゼンチン、コロンビア、エジプト、インド、アイルランド、メキシコ、ナイジェリア、 サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン |
|
| ●第3カテゴリー | その国を指名すれば世界のすべての主要な地理的地域が理事会に代表されることになる国(13カ国) |
| アルジェリア、 カーボヴェルデ、コンゴ共和国、キューバ、エクアドル、ケニア、マレーシア、パナマ、韓国、 トルコ、アラブ首長国連邦、タンザニア、ウルグアイ |
日本は「第1カテゴリー」の中の一角を担い、ICAOの組織運営や活動に必要な予算についても、加盟国全体の中でも第3位の分担額を拠出し、世界の民間航空輸送の安定と発展のために貢献しています(2017年一般予算ベース)。理事会の下には、国際民間航空輸送の大枠となるシカゴ条約や理事会決定により設置された各種の委員会がありICAO日本政府代表部では、理事会代表を中心に外務省や国土交通省と連携をとりつつ、 ICAOの活動の方向性を示す政策議論に積極的に参画しています。
日頃はICAOの存在を身近に感じることが少ないかもしれませんが、皆様が海外旅行に出掛ける際に利用する民間航空機の運航に関連するさまざまな国際規定は、モントリオールのICAO本部で審議、制定され、日本をはじめ世界各国はこれに基づいて国内法令や規則を整備しています。航空機の安全運航に関わる技術的な問題はもちろん、ハイジャックやテロなどの不法行為に対する機内や空港における保安対策、円滑な国際航空輸送の便宜を図るための出入国管理システムの整備に関する問題もICAOが取り扱う重要な問題の一つです。
卑近な例で言いますと、皆様が航空機を利用する際に目にする空港の滑走路や誘導路の仕様、搭乗前の手荷物保安検査の手順や仕様、パスポートの作成や発行の仕様なども全てICAOで決められた規則に従って整備されているのです。また最近では環境対策の大きな柱として、ICAOとして国際民間航空分野における地球温暖化抑止のため、航空機の燃料効率を毎年2%改善させ、2020年以降はCO2の総排出量を増加させないことを目標として、市場メカニズムを活用した排出権取引を取り入れた新たな枠組みを設定し、各国に対して環境への負荷の少ない機材や代替燃料の導入を積極的に働きかけています。


また理事会代表の活動は会議の場だけではありません。ICAO本部には理事国以外の国を含む約60カ国が代表部を開設しており、日頃から他国代表部や理事会議長、ICAO事務局長、 事務局職員とコミュニケーションを図ることで、信頼関係を構築し、情報収集や意見交換、ICAO会議での協力要請などを行っています。とりわけアジア太平洋地域の理事国や主要先進国の代表部とは、頻繁に打ち合わせを行い緊密な関係を維持しています。さまざまな課題が山積する中、非力ではありますが、「縁の下の力持ち」として日本政府代表部を支え、これまで皆様へ航空サービスを提供する立場から、今度は日本そして世界の民間航空分野の安全と発展のための国際基準を創り出し、普及させる役目に貢献できるよう頑張ります。